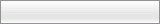| 文献ID |
見出し |
著者 |
文献名 |
出典 |
| 7273 |
しむ(助動詞・接尾語) |
湯沢幸吉郎 |
「足利期の敬語助動詞シモ・シムに就いて」 |
『国語国文の研究』昭4・9=『国語史概説』昭18・1八木書店 |
| 7274 |
しむ(助動詞・接尾語) |
山田孝雄 |
『漢文の訓読によりて伝へられたる語法』 |
昭10・5宝文館 |
| 7275 |
しむ(助動詞・接尾語) |
堀田要治 |
「今昔物語集に於ける使役の助動詞ス・サス・シムについて」 |
『橋本博士還暦記念国語学論集』昭19・10岩波書店 |
| 7276 |
しむ(助動詞・接尾語) |
榎克明 |
「再帰的助動詞〈しむ〉―シンラン研究のついで」 |
大阪大『語文』17昭31・7 |
| 7277 |
しむ(助動詞・接尾語) |
桜井光昭 |
「いわゆる使役・尊敬の助動詞―〈しむ〉の研究」 |
『国文学解釈と教材の研究』4-2昭34・1 |
| 7278 |
しむ(助動詞・接尾語) |
山崎良幸 |
「受身・使役の助動詞る・らる・す・さす・しむ」 |
『国文学解釈と鑑賞』28-7昭38・6 |
| 7279 |
しむ(助動詞・接尾語) |
長谷川清喜 |
「使役ス・サス・シムの〈随従〉的用法について」 |
『語学文学会紀要』1昭39・3 |
| 7280 |
しむ(助動詞・接尾語) |
長谷川清喜 |
「使役の助動詞―す・さす・しむ〈古典語〉」 |
『国文学解釈と教材の研究』9-13昭39・10 |
| 7281 |
しむ(助動詞・接尾語) |
森野宗明 |
「敬譲(含丁寧)の助動詞〈古典語〉」 |
『国文学解釈と教材の研究』9-13昭39・10 |
| 7282 |
しむ(助動詞・接尾語) |
片岡了 |
「中世における〈シム〉の一用法」 |
『大谷学報』40-4昭40・3 |
| 7283 |
しむ(助動詞・接尾語) |
山崎馨 |
「形容詞系助動詞の成立(2)」 |
『国語と国文学』42-3昭40・3 |
| 7284 |
しむ(助動詞・接尾語) |
中川浩文 |
「三帖和讃における〈しむ〉の用法」 |
『女子大国文』87昭40・5 |
| 7285 |
しむ(助動詞・接尾語) |
峰岸明 |
「特集・日本語の助動詞の役割自発・可能・受身・尊敬・使役」 |
『国文学解釈と鑑賞』33-12昭43・10 |
| 7286 |
しむ(助動詞・接尾語) |
道本武彦 |
「〈芭蕉・蕪村・一茶〉発句の助動詞〈る〉〈らる〉〈す〉〈さす〉〈しむ〉〈れる〉〈せる〉について」 |
国学院大『国語研究』27昭44・3 |
| 7287 |
しむ(助動詞・接尾語) |
阪口勝子 |
「今昔物語集における使役の助動詞す・さす・しむの考察」 |
『文芸と思想』35昭46・12 |
| 7288 |
しむ(助動詞・接尾語) |
吉田金彦 |
『上代助動詞の史的研究』 |
昭48・3明治書院 |
| 7289 |
しむ(助動詞・接尾語) |
近藤政美 |
「平家物語における助動詞〈しむ〉の意味用法について」 |
『国語国文学論集松村博司教授定年退官記念』昭48・4名大国語国文学会 |
| 7290 |
しむ(助動詞・接尾語) |
後藤和彦 |
「上代語の助動詞〈ゆ・しむ・す・ふ〉の働きについて」 |
『奈良女大研究年報』17昭49・3 |
| 7291 |
しむ(助動詞・接尾語) |
松下貞三 |
「吾妻鏡における〈令(シム)〉の考察―漢文和化の道をたずねて」 |
『国語と国文学』52-5昭50・5 |
| 7292 |
しむ(助動詞・接尾語) |
松下貞三 |
「使役表現シム〈令・使等〉を通してみた上代散文」 |
『国語国文』46-4昭52・4 |
| 7293 |
しむ(助動詞・接尾語) |
重見一行 |
「親鸞の和讃における〈シム〉の用法―鎌倉期和歌漢文中の〈令〉に関する試論」 |
『国語国文』46-10昭52・10 |
| 7294 |
しむ(助動詞・接尾語) |
岡崎和夫 |
「平安時代の漢文訓読に受け継がれた〈シム〉接続に関する破格例とその特質」 |
『国語学』116昭54・3 |
| 7295 |
しむ(助動詞・接尾語) |
堀畑正臣 |
「平安時代の記録体漢文における〈令(シム)〉について―貞信公記を中心として」 |
『国語国文研究と教育』9昭56・1 |
| 7296 |
しむ(助動詞・接尾語) |
来田隆 |
「和化漢文に於ける〈令〉の一用法」 |
『鎌倉時代語研究5』昭57・5武蔵野書院 |