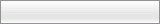| 資料名 |
発行年月(日) |
掲載位置 |
欄名・
連載名等 |
執筆者 |
題名 |
内容 |
コード |
キーワード |
備考 |
| 文藝春秋 |
1923年6月 |
3-4 |
|
中村武羅夫 |
「パパ」「ママ」を難ず |
両親を呼ぶ「パパ」「ママ」ほか、万事が安易に西洋風になることを批判する。 |
親族語彙 外来語・外国語制限 言語意識 新語・流行語 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1923年7月 |
13-14 |
|
平野青夜 |
「パパ」「ママ」を弁護す(奨励に非ず) 中村武羅夫氏に(下) |
6月号の中村に対し、新しいものを排することへの疑問を呈しパパママを弁護するも、自身の子にはエスペラントのパーチョ、パーニョを使わせたい、とする。 |
親族語彙 外来語 言語意識 人工言語 新語・流行語 |
ママ |
上中下のうち下のみを掲載 |
| 文藝春秋 |
1923年7月 |
14-15 |
|
丸山室夫 |
「パパ」「ママ」は何処の国の語か |
英米の子供もパパママは使わずダディ、マミイを使うのに、乳児でもない日本人の子供がパパママを使うのは愚劣である、とする。 |
親族語彙 外来語 言語意識 新語・流行語 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1923年8月 |
11-11 |
|
鴻原駿 |
妄言 |
カンプロマイズが間違いであることを再主張し、パパママはどうでもいい問題、とする。 |
外来語の表記 親族語彙 外来語 言語意識 新語・流行語 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1933年5月 |
138-164 |
|
巌谷小波、岸田国士、久米正雄ほか |
明治大正昭和文芸座談会 |
「改訂小学読本」教科書に書いた文章は、文部省に去勢されてしまう。「パパ・ママ論」文士でも子供が「パパ・ママ」を使う家庭が多い。「スタイル論」「文章の進展」「露伴・紅葉・花袋」作家の文体と、今日の文体への硯友社の影響について。(152) |
親族語彙 国語教育 教育政策 ジャンルによる文体 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1934年10月 |
60-61 |
社会春秋 |
|
|
松田文相の「パパ・ママ」追放案について、その考え方なら日本娘がパンツをはきハードルを跳ぶオリンピックもダメなことになる、と揶揄する。 |
親族語彙 呼称 外来語・外国語制限 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1934年10月 |
294-295 |
目・耳・口 |
|
耳 |
松田文相の「パパ・ママ」批判を、「愚にもつかぬ世迷ひ言」と退ける。 |
親族語彙 呼称 外来語・外国語制限 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1935年7月 |
6-7 |
随筆 |
植原悦二郎 |
腑に落ちぬ事 |
小児がパパ・ママと言ったところで孝行の大義を失うことはない。それを言うならメートル法も、洋館に住み洋服を着て洋書を読むことも禁止するべきだ。 |
呼称 幼児語 親族語彙 外来語・外国語制限 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1935年8月 |
180-184 |
現代語考 |
岡倉由三郎 |
ことばはゆらぐ |
明治以降の風俗の変化を概観し、さらに言葉遣いの変化について、「パパ・ママ」を容認し、外来語や若者語も冷静に評価しつつ述べる。 |
国語問題一般 新語・流行語 若者語 外来語・外国語制限 |
パパ・ママ |
|
| 文藝春秋 |
1935年8月 |
222-224 |
二階堂放話 |
久米正雄 |
|
松田文相の「パパ・ママ」排斥を排外思想と批判し、自分の家庭では幼児語としてのみ使わせており、「パパ・ママ廃すべからず。是を幼語とせよ」としめくくる。 |
外来語・外国語制限 呼称 親族語彙 幼児語 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1935年9月 |
16-17 |
随筆 |
桑田芳蔵 |
言外の意味 |
俳句や諺、さらには語や文章にも「言外の意味」というものがあり、それを翻訳するのは難しい。「パパ・ママ」の流行は単なる外国模倣でなく、親子関係の心理的推移の結果である。 |
翻訳 詩歌 ことわざ 外来語 親族名称 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1936年3月 |
186-193 |
|
林房雄 |
小泉三申閑談録 |
「松田文相の追憶」林と小泉策太郎との対談録で、小泉が、駅名の横書きの仕方や仮名遣い、さらにパパ・ママ等の外来語の使用についての持論を述べる。(191-3) |
国字問題(その他) 仮名遣い 文字・表記(その他) 外来語・外国語制限 親族語彙 |
ママ |
|
| 文藝春秋 |
1938年11月 |
25-26 |
随筆 |
村松正俊 |
東京語の変化 |
東京生まれの自分は、日本をニッポン、店の「いらっしゃいませ」、肯定で使う「とても」、パパ・ママ、「ねえ」のアクセントなど変化している今の東京語に不満がある。 |
方言(東京) 標準語 言語意識 |
ママ |
|