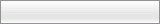| 文献ID |
見出し |
著者 |
文献名 |
出典 |
| 844 |
あわれ(哀) |
松村博 |
「浜松中納言物語と更級日記における〈あはれ〉について」 |
『日本文学研究』昭25・5 |
| 845 |
あわれ(哀) |
上村悦子 |
「〈あはれ〉について」 |
『日本女子大学紀要』1昭26・10 |
| 846 |
あわれ(哀) |
大西善明 |
「源氏語彙〈あはれ〉一覧」 |
『平安文学研究』9昭27・5 |
| 847 |
あわれ(哀) |
池田義孝 |
「〈をかし〉と〈あはれ〉について」 |
『愛媛国語国文』昭28・1 |
| 848 |
あわれ(哀) |
山口晃 |
「平安朝諸日記にみえる〈あはれ〉と〈をかし〉の全貌」 |
『平安文学研究』12昭28・6 |
| 849 |
あわれ(哀) |
井上豊 |
「〈もののあはれ〉の意味とヒューマニズム」 |
『国語と国文学』31-1昭29・1 |
| 850 |
あわれ(哀) |
楠道隆 |
「枕草子における〈あはれ〉について」 |
『国文論叢』昭29・11 |
| 851 |
あわれ(哀) |
Hisamatsu, S. |
“The Vocabulary of Japanese Literary Aesthetics” |
Centre for East Asian Cultural Studies昭38 |
| 852 |
あわれ(哀) |
田中高志 |
「平家物語における〈あはれ〉と〈むざん〉について」 |
『国語教育研究』7昭38・5 |
| 853 |
あわれ(哀) |
川辺為三 |
「源氏物語〈あはれ〉考―あはれにをかしの解釈」 |
『国文学解釈と教材の研究』8-14昭38・11 |
| 854 |
あわれ(哀) |
亀山泰紀 |
「枕草子の〈あはれ〉―四系統諸伝本の比較」 |
『中世文芸』28昭38・11 |
| 855 |
あわれ(哀) |
新妻順子 |
「和泉式部日記の心情表現―〈はかなし〉〈あはれ〉〈つれづれ〉の意識について」 |
『日本文学ノート』1昭40・12 |
| 856 |
あわれ(哀) |
小野村洋子 |
「源氏物語における〈あはれ〉の一課題」 |
『共立女子大紀要』12昭41・11=『源氏物語の精神的基底』昭45・4創文社 |
| 857 |
あわれ(哀) |
仲岡睦 |
「徒然草の一考察―あはれを通して」 |
『女子大国文』44昭42・2 |
| 858 |
あわれ(哀) |
岩淵悦太郎 |
『語源散策』 |
昭49・10毎日新聞社 |
| 859 |
あわれ(哀) |
浜田美智子 |
「源氏物語における〈あはれ〉の研究」 |
『国語の研究』3昭43・3 |
| 860 |
あわれ(哀) |
進藤義治 |
「文芸用語〈あはれ〉の諸語形について」 |
『名古屋大学国語国文学』32昭43・11 |
| 861 |
あわれ(哀) |
野口進 |
「平家物語に於ける〈あはれ〉の考察」 |
『金城学院大学論集』37昭43・12 |
| 862 |
あわれ(哀) |
進藤義治 |
「六歌集歌における名詞〈あはれ〉頻用に関する考察1・2」 |
『名古屋大学国語国文学』2526昭44・12、45・7 |
| 863 |
あわれ(哀) |
吉永亜美 |
「平家物語の〈あはれ〉―王朝物語の継承と展開」 |
『女子大国文』57昭45・5 |
| 864 |
あわれ(哀) |
重松信弘 |
「源氏物語の〈あはれ〉と〈物のあはれ〉」 |
梅光女学院大『国文学研究』6昭45・11 |
| 865 |
あわれ(哀) |
進藤義治 |
「源氏物語散文中の名詞〈あはれ〉について」 |
『名古屋大学国語国文学』27昭45・12 |
| 866 |
あわれ(哀) |
三田村紀子 |
「無相の語」 |
『奈良女子大学文学部研究年報』14昭46・3 |
| 867 |
あわれ(哀) |
進藤義治 |
「源氏物語の用語〈あはれ〉のオリジナリティ」 |
『名古屋大学国語国文学』28昭46・7 |
| 868 |
あわれ(哀) |
小野村洋子 |
「〈あはれ〉の構造についての試論―その広さと奥行きの整序のための序論として」 |
『共立女子大文学部紀要』19昭47・3 |
| 869 |
あわれ(哀) |
上村悦子 |
「私の卒業論文〈あはれとをかしとおもしろしの考察〉」 |
『解釈と鑑賞』38-1昭48・1 |
| 870 |
あわれ(哀) |
吉沢義則 |
『増補源語釈泉』 |
昭48・5臨川書店 |
| 871 |
あわれ(哀) |
星加文子 |
「〈あはれ〉についての考察」 |
『立教大学日本文学』30昭48・6 |
| 872 |
あわれ(哀) |
押見虎三二 |
「〈あはれ〉論に関する覚書」 |
『新大国語』2昭50・3 |
| 873 |
あわれ(哀) |
竹西寛子 |
「〈あはれ〉から〈もののあはれ〉へ」 |
『言語生活』296昭51・7 |
| 874 |
あわれ(哀) |
吉田金彦 |
「万葉のことばと文学(2)〈あはれ〉と〈をかし〉」 |
『短歌研究』33-9昭51・9 |
| 875 |
あわれ(哀) |
片山武 |
「〈如是𪫧怜〉(④746)万葉の〈あはれ〉と〈あもしろし〉について」 |
『解釈』24-1昭53・1 |
| 876 |
あわれ(哀) |
馬場あき子 |
「言語時評あはれ・あわれ」 |
『言語生活』323昭53・11 |
| 877 |
あわれ(哀) |
江沢潤子 |
「源氏物語の〈あはれ〉について」 |
『解釈』25-8昭54・8 |
| 878 |
あわれ(哀) |
江沢潤子 |
「源氏物語の〈あはれ〉の一用法に就いて1・2」 |
『解釈』26-89昭55・89 |
| 879 |
あわれ(哀) |
内田賢徳 |
「副詞〈あはれ〉について―かざし抄ノオト」 |
『帝塚山学院大日本文学研究』12昭56・2 |
| 882 |
―なり |
進藤義治 |
「源氏物語におけるあはれなりの述語用例」 |
『名古屋大学国語国文学』19昭41・11 |
| 883 |
―なり |
藤尾恭子 |
「平家物語〈あはれなり〉の表現価値」 |
『武庫川国文』5昭48・3 |
| 884 |
―なり |
土屋博映 |
「枕草子の〈をかし〉と〈あはれなり〉―情景と動植物の描写から」 |
『佐伯梅友博士喜寿記念国語学論集』昭51・12表現社 |
| 885 |
―なり |
土屋博映 |
「枕草子の〈あはれなり〉〈をかし〉〈めでたし〉」 |
『国語学会昭和52年春季大会発表要旨』昭52・5 |
| 886 |
―なり |
小島俊夫 |
「〈あやし〉〈あはれなり〉の副詞法と中止法」 |
『解釈』24-2昭53・2 |
| 887 |
―なり |
土屋博映 |
「枕草子の美的理念語―〈あはれなり〉〈をかし〉〈めでたし〉を中心として」 |
『中田祝夫博士功績記念国語学論集』昭54・2勉誠社 |