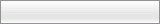| 文献ID |
見出し |
著者 |
文献名 |
出典 |
| 15669 |
もの(物・者) |
土居光知 |
『日本語の姿』 |
昭18・6改造社 |
| 15669 |
もの(物・者) |
土居光知 |
『日本語の姿』 |
昭18・6改造社 |
| 15669 |
もの(物・者) |
土居光知 |
『日本語の姿』 |
昭18・6改造社 |
| 15669 |
もの(物・者) |
土居光知 |
『日本語の姿』 |
昭18・6改造社 |
| 15670 |
もの(物・者) |
小林好日 |
『方言語彙学的研究』 |
昭25・11岩波書店 |
| 15670 |
もの(物・者) |
小林好日 |
『方言語彙学的研究』 |
昭25・11岩波書店 |
| 15670 |
もの(物・者) |
小林好日 |
『方言語彙学的研究』 |
昭25・11岩波書店 |
| 15670 |
もの(物・者) |
小林好日 |
『方言語彙学的研究』 |
昭25・11岩波書店 |
| 15671 |
もの(物・者) |
榊原省三 |
「豊川方言の〈モノ〉」 |
『言語生活』19昭28・4 |
| 15671 |
もの(物・者) |
榊原省三 |
「豊川方言の〈モノ〉」 |
『言語生活』19昭28・4 |
| 15671 |
もの(物・者) |
榊原省三 |
「豊川方言の〈モノ〉」 |
『言語生活』19昭28・4 |
| 15671 |
もの(物・者) |
榊原省三 |
「豊川方言の〈モノ〉」 |
『言語生活』19昭28・4 |
| 15672 |
もの(物・者) |
西下経一 |
「源氏物語の〈もの〉」 |
『国語と国文学』31-1昭29・1 |
| 15672 |
もの(物・者) |
西下経一 |
「源氏物語の〈もの〉」 |
『国語と国文学』31-1昭29・1 |
| 15672 |
もの(物・者) |
西下経一 |
「源氏物語の〈もの〉」 |
『国語と国文学』31-1昭29・1 |
| 15672 |
もの(物・者) |
西下経一 |
「源氏物語の〈もの〉」 |
『国語と国文学』31-1昭29・1 |
| 15673 |
もの(物・者) |
中保進 |
「〈世界〉を意味する道元の〈もの〉」 |
『古典』2昭32・4 |
| 15673 |
もの(物・者) |
中保進 |
「〈世界〉を意味する道元の〈もの〉」 |
『古典』2昭32・4 |
| 15673 |
もの(物・者) |
中保進 |
「〈世界〉を意味する道元の〈もの〉」 |
『古典』2昭32・4 |
| 15673 |
もの(物・者) |
中保進 |
「〈世界〉を意味する道元の〈もの〉」 |
『古典』2昭32・4 |
| 15674 |
もの(物・者) |
高森亜美 |
「源氏物語〈もの〉考―その構成と内容」 |
『女子大国文』7昭32・11 |
| 15674 |
もの(物・者) |
高森亜美 |
「源氏物語〈もの〉考―その構成と内容」 |
『女子大国文』7昭32・11 |
| 15674 |
もの(物・者) |
高森亜美 |
「源氏物語〈もの〉考―その構成と内容」 |
『女子大国文』7昭32・11 |
| 15674 |
もの(物・者) |
高森亜美 |
「源氏物語〈もの〉考―その構成と内容」 |
『女子大国文』7昭32・11 |
| 15675 |
もの(物・者) |
西下経一 |
「源氏物語の〈世〉と〈物〉」 |
『文学・語学』6昭32・12 |
| 15675 |
もの(物・者) |
西下経一 |
「源氏物語の〈世〉と〈物〉」 |
『文学・語学』6昭32・12 |
| 15675 |
もの(物・者) |
西下経一 |
「源氏物語の〈世〉と〈物〉」 |
『文学・語学』6昭32・12 |
| 15675 |
もの(物・者) |
西下経一 |
「源氏物語の〈世〉と〈物〉」 |
『文学・語学』6昭32・12 |
| 15676 |
もの(物・者) |
佐藤茂 |
「〈もの〉と〈道理〉」 |
『福井大学学芸学部紀要』8昭33・12 |
| 15676 |
もの(物・者) |
佐藤茂 |
「〈もの〉と〈道理〉」 |
『福井大学学芸学部紀要』8昭33・12 |
| 15676 |
もの(物・者) |
佐藤茂 |
「〈もの〉と〈道理〉」 |
『福井大学学芸学部紀要』8昭33・12 |
| 15676 |
もの(物・者) |
佐藤茂 |
「〈もの〉と〈道理〉」 |
『福井大学学芸学部紀要』8昭33・12 |
| 15677 |
もの(物・者) |
門前正彦 |
「漢文訓読史上の一問題(2)〈ヒト〉より〈モノ〉へ」 |
『訓点語と訓点資料』11昭34・3 |
| 15677 |
もの(物・者) |
門前正彦 |
「漢文訓読史上の一問題(2)〈ヒト〉より〈モノ〉へ」 |
『訓点語と訓点資料』11昭34・3 |
| 15677 |
もの(物・者) |
門前正彦 |
「漢文訓読史上の一問題(2)〈ヒト〉より〈モノ〉へ」 |
『訓点語と訓点資料』11昭34・3 |
| 15677 |
もの(物・者) |
門前正彦 |
「漢文訓読史上の一問題(2)〈ヒト〉より〈モノ〉へ」 |
『訓点語と訓点資料』11昭34・3 |
| 15678 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「〈もの〉を前項とする連語の検討―中古語の場合」 |
『論究日本文学』19昭37・11 |
| 15678 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「〈もの〉を前項とする連語の検討―中古語の場合」 |
『論究日本文学』19昭37・11 |
| 15678 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「〈もの〉を前項とする連語の検討―中古語の場合」 |
『論究日本文学』19昭37・11 |
| 15678 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「〈もの〉を前項とする連語の検討―中古語の場合」 |
『論究日本文学』19昭37・11 |
| 15679 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「〈もの〉複合形容詞の意義―源氏物語の用例を中心として」 |
『国語教育研究』9昭39・12 |
| 15679 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「〈もの〉複合形容詞の意義―源氏物語の用例を中心として」 |
『国語教育研究』9昭39・12 |
| 15679 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「〈もの〉複合形容詞の意義―源氏物語の用例を中心として」 |
『国語教育研究』9昭39・12 |
| 15679 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「〈もの〉複合形容詞の意義―源氏物語の用例を中心として」 |
『国語教育研究』9昭39・12 |
| 15680 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「源氏物語・枕草子における〈もの〉語彙・〈こと〉語彙―語彙研究の方法についての試論」 |
『国文学攷』39昭41・3 |
| 15680 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「源氏物語・枕草子における〈もの〉語彙・〈こと〉語彙―語彙研究の方法についての試論」 |
『国文学攷』39昭41・3 |
| 15680 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「源氏物語・枕草子における〈もの〉語彙・〈こと〉語彙―語彙研究の方法についての試論」 |
『国文学攷』39昭41・3 |
| 15680 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「源氏物語・枕草子における〈もの〉語彙・〈こと〉語彙―語彙研究の方法についての試論」 |
『国文学攷』39昭41・3 |
| 15681 |
もの(物・者) |
船田逸夫 |
「モノとコト」 |
『言語生活』218昭44・11 |
| 15681 |
もの(物・者) |
船田逸夫 |
「モノとコト」 |
『言語生活』218昭44・11 |
| 15681 |
もの(物・者) |
船田逸夫 |
「モノとコト」 |
『言語生活』218昭44・11 |
| 15681 |
もの(物・者) |
船田逸夫 |
「モノとコト」 |
『言語生活』218昭44・11 |
| 15682 |
もの(物・者) |
野村和世 |
「狂言の〈留め〉に用いる〈もの〉について」 |
国学院大『国語研究』30昭45・12 |
| 15682 |
もの(物・者) |
野村和世 |
「狂言の〈留め〉に用いる〈もの〉について」 |
国学院大『国語研究』30昭45・12 |
| 15682 |
もの(物・者) |
野村和世 |
「狂言の〈留め〉に用いる〈もの〉について」 |
国学院大『国語研究』30昭45・12 |
| 15682 |
もの(物・者) |
野村和世 |
「狂言の〈留め〉に用いる〈もの〉について」 |
国学院大『国語研究』30昭45・12 |
| 15683 |
もの(物・者) |
高橋俊三 |
「琉球方言の接続助詞〈こと〉〈もの〉について」 |
『国際大学国文学』4昭47・3 |
| 15683 |
もの(物・者) |
高橋俊三 |
「琉球方言の接続助詞〈こと〉〈もの〉について」 |
『国際大学国文学』4昭47・3 |
| 15683 |
もの(物・者) |
高橋俊三 |
「琉球方言の接続助詞〈こと〉〈もの〉について」 |
『国際大学国文学』4昭47・3 |
| 15683 |
もの(物・者) |
高橋俊三 |
「琉球方言の接続助詞〈こと〉〈もの〉について」 |
『国際大学国文学』4昭47・3 |
| 15684 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安時代の連語の意味・用法―物の様・事の様、物の紛れ・事の紛れ、物の初め・事の初め、物のついで・事のついで」 |
『河』5昭48・6 |
| 15684 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安時代の連語の意味・用法―物の様・事の様、物の紛れ・事の紛れ、物の初め・事の初め、物のついで・事のついで」 |
『河』5昭48・6 |
| 15684 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安時代の連語の意味・用法―物の様・事の様、物の紛れ・事の紛れ、物の初め・事の初め、物のついで・事のついで」 |
『河』5昭48・6 |
| 15684 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安時代の連語の意味・用法―物の様・事の様、物の紛れ・事の紛れ、物の初め・事の初め、物のついで・事のついで」 |
『河』5昭48・6 |
| 15685 |
もの(物・者) |
豊田知加子 |
「平安朝文学における語彙について―〈もの〉複合形容詞について」 |
『大谷女子大国文』4昭49・3 |
| 15685 |
もの(物・者) |
豊田知加子 |
「平安朝文学における語彙について―〈もの〉複合形容詞について」 |
『大谷女子大国文』4昭49・3 |
| 15685 |
もの(物・者) |
豊田知加子 |
「平安朝文学における語彙について―〈もの〉複合形容詞について」 |
『大谷女子大国文』4昭49・3 |
| 15685 |
もの(物・者) |
豊田知加子 |
「平安朝文学における語彙について―〈もの〉複合形容詞について」 |
『大谷女子大国文』4昭49・3 |
| 15686 |
もの(物・者) |
我妻建治 |
「神皇正統記の〈ヒト〉と〈モノ〉―〈童蒙〉補考」 |
『成城文芸』69昭49・4 |
| 15686 |
もの(物・者) |
我妻建治 |
「神皇正統記の〈ヒト〉と〈モノ〉―〈童蒙〉補考」 |
『成城文芸』69昭49・4 |
| 15686 |
もの(物・者) |
我妻建治 |
「神皇正統記の〈ヒト〉と〈モノ〉―〈童蒙〉補考」 |
『成城文芸』69昭49・4 |
| 15686 |
もの(物・者) |
我妻建治 |
「神皇正統記の〈ヒト〉と〈モノ〉―〈童蒙〉補考」 |
『成城文芸』69昭49・4 |
| 15687 |
もの(物・者) |
井上勇 |
「漢語和語―物と事について」 |
九州大谷短大『国語研究』3昭49・12 |
| 15687 |
もの(物・者) |
井上勇 |
「漢語和語―物と事について」 |
九州大谷短大『国語研究』3昭49・12 |
| 15687 |
もの(物・者) |
井上勇 |
「漢語和語―物と事について」 |
九州大谷短大『国語研究』3昭49・12 |
| 15687 |
もの(物・者) |
井上勇 |
「漢語和語―物と事について」 |
九州大谷短大『国語研究』3昭49・12 |
| 15688 |
もの(物・者) |
大野晋 |
「〈もの〉という言葉」 |
『講座古代学』昭50・1中央公論社 |
| 15688 |
もの(物・者) |
大野晋 |
「〈もの〉という言葉」 |
『講座古代学』昭50・1中央公論社 |
| 15688 |
もの(物・者) |
大野晋 |
「〈もの〉という言葉」 |
『講座古代学』昭50・1中央公論社 |
| 15688 |
もの(物・者) |
大野晋 |
「〈もの〉という言葉」 |
『講座古代学』昭50・1中央公論社 |
| 15689 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安時代語としての〈ひと〉と〈もの〉」 |
高知大『国語教育』22昭50・1 |
| 15689 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安時代語としての〈ひと〉と〈もの〉」 |
高知大『国語教育』22昭50・1 |
| 15689 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安時代語としての〈ひと〉と〈もの〉」 |
高知大『国語教育』22昭50・1 |
| 15689 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安時代語としての〈ひと〉と〈もの〉」 |
高知大『国語教育』22昭50・1 |
| 15690 |
もの(物・者) |
|
「文化ジャーナル・文学日本語の〈コト〉と〈モノ〉と」 |
『朝日ジャーナル』昭50・6・6 |
| 15690 |
もの(物・者) |
|
「文化ジャーナル・文学日本語の〈コト〉と〈モノ〉と」 |
『朝日ジャーナル』昭50・6・6 |
| 15690 |
もの(物・者) |
|
「文化ジャーナル・文学日本語の〈コト〉と〈モノ〉と」 |
『朝日ジャーナル』昭50・6・6 |
| 15690 |
もの(物・者) |
|
「文化ジャーナル・文学日本語の〈コト〉と〈モノ〉と」 |
『朝日ジャーナル』昭50・6・6 |
| 15691 |
もの(物・者) |
江口智万 |
「上代における〈こと〉と〈もの〉―万葉集の〈ことあげ〉」 |
『薩摩路』20昭51・3 |
| 15691 |
もの(物・者) |
江口智万 |
「上代における〈こと〉と〈もの〉―万葉集の〈ことあげ〉」 |
『薩摩路』20昭51・3 |
| 15691 |
もの(物・者) |
江口智万 |
「上代における〈こと〉と〈もの〉―万葉集の〈ことあげ〉」 |
『薩摩路』20昭51・3 |
| 15691 |
もの(物・者) |
江口智万 |
「上代における〈こと〉と〈もの〉―万葉集の〈ことあげ〉」 |
『薩摩路』20昭51・3 |
| 15692 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「漢文訓読語の一面〈者〉を〈モノ〉と訓むことの意味」 |
『大坪併治教授退官記念国語史論集』昭51・5表現社 |
| 15692 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「漢文訓読語の一面〈者〉を〈モノ〉と訓むことの意味」 |
『大坪併治教授退官記念国語史論集』昭51・5表現社 |
| 15692 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「漢文訓読語の一面〈者〉を〈モノ〉と訓むことの意味」 |
『大坪併治教授退官記念国語史論集』昭51・5表現社 |
| 15692 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「漢文訓読語の一面〈者〉を〈モノ〉と訓むことの意味」 |
『大坪併治教授退官記念国語史論集』昭51・5表現社 |
| 15693 |
もの(物・者) |
木坂基 |
「近代文章における〈こと〉表現・〈もの〉表現」 |
『国語学』105昭51・6 |
| 15693 |
もの(物・者) |
木坂基 |
「近代文章における〈こと〉表現・〈もの〉表現」 |
『国語学』105昭51・6 |
| 15693 |
もの(物・者) |
木坂基 |
「近代文章における〈こと〉表現・〈もの〉表現」 |
『国語学』105昭51・6 |
| 15693 |
もの(物・者) |
木坂基 |
「近代文章における〈こと〉表現・〈もの〉表現」 |
『国語学』105昭51・6 |
| 15694 |
もの(物・者) |
森重敏 |
「ひと(人)かそ(父)おや(親・祖)付けたり―オニ・モノ・タマ・カミについて」 |
『万葉』93昭51・12 |
| 15694 |
もの(物・者) |
森重敏 |
「ひと(人)かそ(父)おや(親・祖)付けたり―オニ・モノ・タマ・カミについて」 |
『万葉』93昭51・12 |
| 15694 |
もの(物・者) |
森重敏 |
「ひと(人)かそ(父)おや(親・祖)付けたり―オニ・モノ・タマ・カミについて」 |
『万葉』93昭51・12 |
| 15694 |
もの(物・者) |
森重敏 |
「ひと(人)かそ(父)おや(親・祖)付けたり―オニ・モノ・タマ・カミについて」 |
『万葉』93昭51・12 |
| 15695 |
もの(物・者) |
安達隆一 |
「名詞句構造における〈モノ〉〈コト〉〈ノ〉―統語論的構造の差異を中心として」 |
『国語国文学報』31昭52・3 |
| 15695 |
もの(物・者) |
安達隆一 |
「名詞句構造における〈モノ〉〈コト〉〈ノ〉―統語論的構造の差異を中心として」 |
『国語国文学報』31昭52・3 |
| 15695 |
もの(物・者) |
安達隆一 |
「名詞句構造における〈モノ〉〈コト〉〈ノ〉―統語論的構造の差異を中心として」 |
『国語国文学報』31昭52・3 |
| 15695 |
もの(物・者) |
安達隆一 |
「名詞句構造における〈モノ〉〈コト〉〈ノ〉―統語論的構造の差異を中心として」 |
『国語国文学報』31昭52・3 |
| 15696 |
もの(物・者) |
我妻建治 |
「〈ヒト〉と〈モノ〉考(1)増鏡の場合」 |
『成城大短大学部紀要』8昭52・8 |
| 15696 |
もの(物・者) |
我妻建治 |
「〈ヒト〉と〈モノ〉考(1)増鏡の場合」 |
『成城大短大学部紀要』8昭52・8 |
| 15696 |
もの(物・者) |
我妻建治 |
「〈ヒト〉と〈モノ〉考(1)増鏡の場合」 |
『成城大短大学部紀要』8昭52・8 |
| 15696 |
もの(物・者) |
我妻建治 |
「〈ヒト〉と〈モノ〉考(1)増鏡の場合」 |
『成城大短大学部紀要』8昭52・8 |
| 15697 |
もの(物・者) |
神川正彦 |
「〈こと〉と〈もの〉―言葉と〈もの―ごと〉」 |
『国学院雑誌』78-10昭52・10 |
| 15697 |
もの(物・者) |
神川正彦 |
「〈こと〉と〈もの〉―言葉と〈もの―ごと〉」 |
『国学院雑誌』78-10昭52・10 |
| 15697 |
もの(物・者) |
神川正彦 |
「〈こと〉と〈もの〉―言葉と〈もの―ごと〉」 |
『国学院雑誌』78-10昭52・10 |
| 15697 |
もの(物・者) |
神川正彦 |
「〈こと〉と〈もの〉―言葉と〈もの―ごと〉」 |
『国学院雑誌』78-10昭52・10 |
| 15698 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「源氏物語の〈わざ〉―〈こと〉〈もの〉との関係」 |
『源氏物語の探究3』昭52・11風間書房 |
| 15698 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「源氏物語の〈わざ〉―〈こと〉〈もの〉との関係」 |
『源氏物語の探究3』昭52・11風間書房 |
| 15698 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「源氏物語の〈わざ〉―〈こと〉〈もの〉との関係」 |
『源氏物語の探究3』昭52・11風間書房 |
| 15698 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「源氏物語の〈わざ〉―〈こと〉〈もの〉との関係」 |
『源氏物語の探究3』昭52・11風間書房 |
| 15699 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「教行信証における〈ヒト〉と〈モノ〉―〈者〉の訓をとおして」 |
『鎌倉時代語研究3』昭55・3 |
| 15699 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「教行信証における〈ヒト〉と〈モノ〉―〈者〉の訓をとおして」 |
『鎌倉時代語研究3』昭55・3 |
| 15699 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「教行信証における〈ヒト〉と〈モノ〉―〈者〉の訓をとおして」 |
『鎌倉時代語研究3』昭55・3 |
| 15699 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「教行信証における〈ヒト〉と〈モノ〉―〈者〉の訓をとおして」 |
『鎌倉時代語研究3』昭55・3 |
| 15700 |
もの(物・者) |
荒木博之 |
『日本語から日本人を考える』 |
昭55・5朝日新聞社 |
| 15700 |
もの(物・者) |
荒木博之 |
『日本語から日本人を考える』 |
昭55・5朝日新聞社 |
| 15700 |
もの(物・者) |
荒木博之 |
『日本語から日本人を考える』 |
昭55・5朝日新聞社 |
| 15700 |
もの(物・者) |
荒木博之 |
『日本語から日本人を考える』 |
昭55・5朝日新聞社 |
| 15701 |
もの(物・者) |
森田良行 |
『基礎日本語2』 |
昭55・6角川書店 |
| 15701 |
もの(物・者) |
森田良行 |
『基礎日本語2』 |
昭55・6角川書店 |
| 15701 |
もの(物・者) |
森田良行 |
『基礎日本語2』 |
昭55・6角川書店 |
| 15701 |
もの(物・者) |
森田良行 |
『基礎日本語2』 |
昭55・6角川書店 |
| 15702 |
もの(物・者) |
松浦照子 |
「複合形容詞〈うら…〉〈こころ…〉〈もの…〉〈なま…〉の形成―平安女流文学における」 |
『山形女子短大紀要』13昭56・3 |
| 15702 |
もの(物・者) |
松浦照子 |
「複合形容詞〈うら…〉〈こころ…〉〈もの…〉〈なま…〉の形成―平安女流文学における」 |
『山形女子短大紀要』13昭56・3 |
| 15702 |
もの(物・者) |
松浦照子 |
「複合形容詞〈うら…〉〈こころ…〉〈もの…〉〈なま…〉の形成―平安女流文学における」 |
『山形女子短大紀要』13昭56・3 |
| 15702 |
もの(物・者) |
松浦照子 |
「複合形容詞〈うら…〉〈こころ…〉〈もの…〉〈なま…〉の形成―平安女流文学における」 |
『山形女子短大紀要』13昭56・3 |
| 15703 |
もの(物・者) |
此島正年 |
「接続助詞〈もの…〉の語群」 |
『湘南文学』15昭56・3 |
| 15703 |
もの(物・者) |
此島正年 |
「接続助詞〈もの…〉の語群」 |
『湘南文学』15昭56・3 |
| 15703 |
もの(物・者) |
此島正年 |
「接続助詞〈もの…〉の語群」 |
『湘南文学』15昭56・3 |
| 15703 |
もの(物・者) |
此島正年 |
「接続助詞〈もの…〉の語群」 |
『湘南文学』15昭56・3 |
| 15704 |
もの(物・者) |
寺村秀夫 |
「〈モノ〉と〈コト〉」 |
『馬淵和夫博士退官記念国語学論集』昭56・7大修館 |
| 15704 |
もの(物・者) |
寺村秀夫 |
「〈モノ〉と〈コト〉」 |
『馬淵和夫博士退官記念国語学論集』昭56・7大修館 |
| 15704 |
もの(物・者) |
寺村秀夫 |
「〈モノ〉と〈コト〉」 |
『馬淵和夫博士退官記念国語学論集』昭56・7大修館 |
| 15704 |
もの(物・者) |
寺村秀夫 |
「〈モノ〉と〈コト〉」 |
『馬淵和夫博士退官記念国語学論集』昭56・7大修館 |
| 15705 |
もの(物・者) |
大坪併治 |
『平安時代における訓点語の文法』 |
昭56・8風間書房 |
| 15705 |
もの(物・者) |
大坪併治 |
『平安時代における訓点語の文法』 |
昭56・8風間書房 |
| 15705 |
もの(物・者) |
大坪併治 |
『平安時代における訓点語の文法』 |
昭56・8風間書房 |
| 15705 |
もの(物・者) |
大坪併治 |
『平安時代における訓点語の文法』 |
昭56・8風間書房 |
| 15706 |
もの(物・者) |
内田賢徳 |
「よみづめの〈もの〉」 |
『帝塚山学院大研究論集』16昭56・12 |
| 15706 |
もの(物・者) |
内田賢徳 |
「よみづめの〈もの〉」 |
『帝塚山学院大研究論集』16昭56・12 |
| 15706 |
もの(物・者) |
内田賢徳 |
「よみづめの〈もの〉」 |
『帝塚山学院大研究論集』16昭56・12 |
| 15706 |
もの(物・者) |
内田賢徳 |
「よみづめの〈もの〉」 |
『帝塚山学院大研究論集』16昭56・12 |
| 15707 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安朝和歌と〈もの〉形容詞・〈もの〉形容動詞」 |
『国文学攷』95昭57・9 |
| 15707 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安朝和歌と〈もの〉形容詞・〈もの〉形容動詞」 |
『国文学攷』95昭57・9 |
| 15707 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安朝和歌と〈もの〉形容詞・〈もの〉形容動詞」 |
『国文学攷』95昭57・9 |
| 15707 |
もの(物・者) |
東辻保和 |
「平安朝和歌と〈もの〉形容詞・〈もの〉形容動詞」 |
『国文学攷』95昭57・9 |
| 15708 |
もの(物・者) |
藤原与一 |
「名詞系の転成文末詞〈モノ〉」 |
『方言研究年報』続7昭57・12 |
| 15708 |
もの(物・者) |
藤原与一 |
「名詞系の転成文末詞〈モノ〉」 |
『方言研究年報』続7昭57・12 |
| 15708 |
もの(物・者) |
藤原与一 |
「名詞系の転成文末詞〈モノ〉」 |
『方言研究年報』続7昭57・12 |
| 15708 |
もの(物・者) |
藤原与一 |
「名詞系の転成文末詞〈モノ〉」 |
『方言研究年報』続7昭57・12 |
| 15709 |
もの(物・者) |
根来司 |
佐藤喜代治編『講座日本語の語彙3』 |
昭57・5明治書院 |
| 15709 |
もの(物・者) |
根来司 |
佐藤喜代治編『講座日本語の語彙3』 |
昭57・5明治書院 |
| 15709 |
もの(物・者) |
根来司 |
佐藤喜代治編『講座日本語の語彙3』 |
昭57・5明治書院 |
| 15709 |
もの(物・者) |
根来司 |
佐藤喜代治編『講座日本語の語彙3』 |
昭57・5明治書院 |